息切れについて
 息切れとは、身体が酸素不足を感じた時に発するサインです。激しい運動後など、誰でも息切れを経験しますが、何らかの病気が原因の場合、軽い運動や日常動作でも息苦しさを感じることがあります。
息切れとは、身体が酸素不足を感じた時に発するサインです。激しい運動後など、誰でも息切れを経験しますが、何らかの病気が原因の場合、軽い運動や日常動作でも息苦しさを感じることがあります。
息切れの症状は、呼吸回数の増加、時々深呼吸をしないとつらい、睡眠中に息苦しくて目が覚めるなど、人によって感じ方は異なります。
なお、「息苦しさ」や「呼吸困難」といった言葉も、息切れと同じ意味で使用されます。
mMRCスケール(Modified Medical Research Council)息切れスケール
※Grade 2以上の症状が確認される場合には、医療機関への受診をご検討ください。
| Grade0 | 息切れしない |
|---|---|
| Grade1 | 強い労作によって息切れする |
| Grade2 | 平地を早歩きする、または緩やかな坂道を登る際に息切れする |
| Grade3 | 平地歩行速度が同年齢の人より遅い、または平地を歩いた後、息継ぎのために休憩する |
| Grade4 | 約100ヤード歩行後、または数分間の平地歩行後に息継ぎのために休憩する |
| Grade5 | 息切れのため外出が困難、または衣服の着脱でも息切れする |
息切れの原因
人は肺で酸素を血液中に取り込み、心臓のポンプ作用によって、動脈から毛細血管を通して全身の細胞へ酸素を供給します。酸素を細胞に供給した後、毛細血管は二酸化炭素や老廃物を回収し、静脈を通じて肺へ戻し、肺から二酸化炭素を体外へ放出します。この過程において、呼吸による酸素の取り込みや二酸化炭素の排出が円滑に行われない場合、身体に必要な酸素が行き渡らず、息切れが生じます。
また、血液循環に問題がある場合、肺での酸素取り込みは正常でも、末端の細胞へ酸素が十分に届かない状況が発生し、結果として息切れが生じることがあります。
さらに、呼吸と血液循環の両方が正常に機能しているにも関わらず、身体の組織が酸素不足であると誤認識する状態から息切れを引き起こすこともあります。
加齢に伴う体力低下によって息切れを感じることもありますが、以下のような疾患が背景に潜んでいる可能性もあります。息切れが続くようであれば、早期に医療機関を受診することをお勧めします。
息切れの原因疾患
息切れを引き起こす疾患には、以下のようなものが挙げられます。正確な診断は医療機関でのみ可能ですが、早期発見のために、代表的な疾患の特徴をご紹介します。これらの特徴に心当たりのある方は、なるべく早めに当院までご相談ください。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、有害物質の吸入によって引き起こされる疾患で、かつては慢性気管支炎や肺気腫などと呼ばれていました。この疾患の最大の原因は喫煙習慣で、全症例の約90%を占めます。
タバコの煙などの有害物質により、慢性気管支炎や肺気腫を引き起こし、肺の機能が徐々に低下します。これらの症状は長期にわたり進行し、咳や息切れが持続します。重症化すると、呼吸不全に至ることもあります。
また、COPDの患者様がインフルエンザや風邪などの感染症にかかると、病状が急激に悪化する可能性があるため、十分にご注意ください。
気管支喘息
気管支喘息は、気道が慢性的に炎症を起こし、さまざまな刺激に過敏に反応することで発症します。原因にはダニや花粉、ペットの毛、ウイルス感染、運動、ストレスなどがあり、個人差があります。症状としては、咳、喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューという音)、息苦しさ、胸の圧迫感などが繰り返し現れます。特に夜間や早朝に悪化しやすく、重症化すると呼吸困難を引き起こすこともあります。適切な治療と環境調整が重要です。
貧血
貧血は様々な要因によって引き起こされますが、最も一般的なのは鉄欠乏性貧血で、鉄分摂取不足や出血などによる鉄分の過剰な喪失が主な原因です。
鉄欠乏性貧血では、鉄分が不足することで、全身の細胞へ酸素を運搬する役割を担う赤血球中のヘモグロビン生成が阻害され、全身の細胞が酸素不足状態に陥ります。
体内の酸素不足は、息切れ、倦怠感、めまいなどの症状を引き起こします。
心不全
心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送れなくなる状態です。原因には高血圧、心筋梗塞、心筋症、弁膜症、不整脈などがあり、これらが心臓に過度な負担をかけることで発症します。症状は進行度により異なりますが、代表的なものに息切れ、むくみ、倦怠感、動悸、夜間の呼吸困難などがあります。特に階段昇降や歩行時の息切れは初期症状として現れやすく、重症化すると安静時にも呼吸困難を感じるようになります。早期発見と原因に応じた治療、生活習慣の改善が重要です。
狭心症
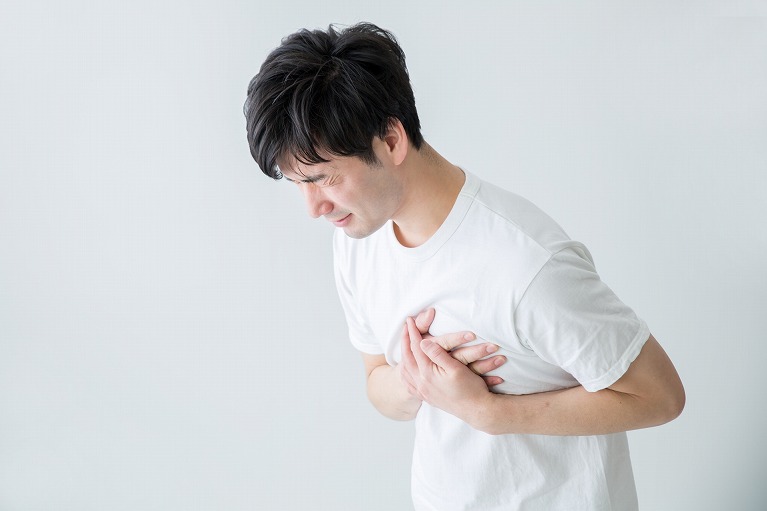
狭心症は、心臓の筋肉に酸素を供給する冠動脈が狭くなり、血流が不足することで胸痛や息切れなどの症状が現れる疾患です。主な原因は動脈硬化で、加齢、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常症などがリスク因子となります。種類には、運動や精神的緊張で発作が起こる「労作性狭心症」、安静時に突然発症する「冠攣縮性狭心症」、発作の頻度や強さが増す「不安定狭心症」があります。症状は胸の圧迫感や痛みに加え、息切れや動悸を伴うこともあり、心筋梗塞への進行を防ぐためにも早期診断と治療が重要です。
不整脈
健康な人の心拍数は1分間に60〜100回程度の規則正しい鼓動とされています。しかし、何らかの原因でこの鼓動が乱れると、心拍数が過剰に増加する頻脈、心拍数が減少する徐脈、または拍動が不規則になる期外収縮などが不整脈として現れます。
頻脈の場合、1分間の心拍数が120回を上回ると、動悸や息切れなどの症状が現れ、重度の場合には意識障害を引き起こすこともあります。一方、徐脈の場合、1分間の心拍数が40回を下回ると、めまいや立ちくらみ、息切れなどの症状が現れ、さらに心拍数が低下すると意識障害に至ることがあります。
不整脈の原因は、自律神経の乱れや心臓疾患などが挙げられます。命を落とす恐れもあるため、注意が必要です。
腎不全
腎臓の機能低下で尿の生成が減少すると、体内の水分量が増加し、むくみの原因となるほか、胸や腹部などの通常は水分が蓄積しない部位にも水が溜まり、胸水や腹水を引き起こします。また、体内に水分が過剰に貯留したり、血管内の水分量が増加したりすることで心臓への負担が増加し、息切れなどの症状が現れます。



