急性腎障害とは
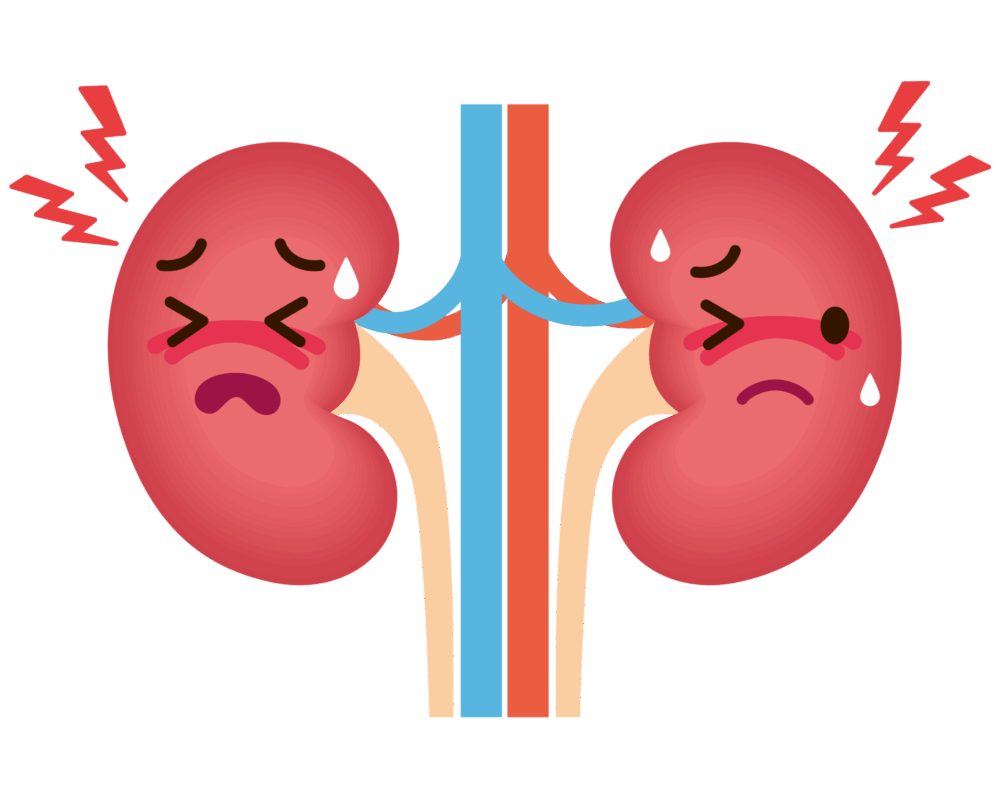 急性腎障害とは、何らかの原因で腎臓の機能が急に低下し、血液中の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなる状態です。多くは脱水や感染、薬剤などがきっかけで発症し、尿量の減少やむくみ、だるさなどの症状が現れます。診断は血清クレアチニン値の急激な上昇や尿量の低下を基準に行い、早期発見が重要です。適切に管理すれば回復することが多いですが、重症化すると慢性腎臓病に移行する恐れもあるため、定期的な検査と生活管理が大切です。
急性腎障害とは、何らかの原因で腎臓の機能が急に低下し、血液中の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなる状態です。多くは脱水や感染、薬剤などがきっかけで発症し、尿量の減少やむくみ、だるさなどの症状が現れます。診断は血清クレアチニン値の急激な上昇や尿量の低下を基準に行い、早期発見が重要です。適切に管理すれば回復することが多いですが、重症化すると慢性腎臓病に移行する恐れもあるため、定期的な検査と生活管理が大切です。
急性腎障害の症状
急性腎障害の症状は、患者様によって様々です。尿量低下が最も一般的な症状ですが、尿量が正常範囲内であっても急性腎障害を発症しているケースも存在します。その他、食欲不振、全身の倦怠感、むくみなどが生じることがあります。
急性腎障害の原因
急性腎障害は、原因によって腎前性、腎性、腎後性に分類されます。
腎前性
腎前性急性腎障害は、全身のどこかに存在する疾患が腎臓への血流を低下させ、腎機能障害を引き起こす病態です。主な原因としては、下痢や出血による体液量の減少、敗血症、心筋梗塞や心不全といった心疾患、不整脈などが挙げられます。
腎性
腎性急性腎障害は、腎機能低下の原因が腎臓自体の障害に由来する病態を指します。腎臓への血流障害、糸球体(血液を濾過して尿を作る働きをする組織)の機能異常、尿細管の損傷、間質性腎炎などが例として挙げられます。
腎後性
腎後性急性腎障害は、腎臓以降の尿路に異常が生じることで発症する病態で、両側尿管の閉塞や膀胱の閉塞などが主な原因として挙げられます。
治療方針は腎障害のタイプによって異なるため、原因特定のため、問診、血液・尿検査を実施します。さらに、超音波検査やCT検査といった画像診断を行い、必要に応じて腎生検が検討されることがあります。
※急性腎障害の原因を調査した結果、外来患者様の場合はおよそ7割が腎前性であり、その主因は脱水や低血圧です。一方、入院患者様の場合は、半数強が腎性であり、薬剤の影響などが要因となります。
急性腎障害の治療
急性腎障害の重症度が高い患者様に対しては、原因を問わず、生命に関わる症状への緊急処置として対症療法が実施されます。例えば、高カリウム血症、高度な体液過剰、代謝性アシドーシス(腎機能の低下により、本来アルカリ性に維持されるべき体内が酸性に傾き、電解質バランスの乱れを引き起こす状態)といった深刻な症状が見られた場合には、原因特定を待たずに、速やかに薬物療法や人工透析が検討されます。
並行して、患者様の病歴、身体診察、各種検査を通して、腎障害のタイプを特定し、直ちに原因に応じた治療を開始します。
腎前性の場合
腎前性急性腎障害の最も一般的な原因は、脱水や低血圧によるものです。これらの要因となる基礎疾患が存在する場合は、その治療を優先しつつ、脱水に対しては速やかに輸液を行い、低血圧に対しては必要に応じて昇圧剤を処方します。
腎性の場合
腎性急性腎障害の中で、血管に炎症が生じ、急速進行性糸球体腎炎を引き起こしている場合には、ステロイド薬による免疫抑制療法、または血漿交換療法による血管炎の原因抗体除去が検討されます。また、腎機能回復までの期間は、腎臓に負担をかける薬剤の服用を中止し、栄養管理を中心とした腎機能サポートが重要となります。
腎後性の場合
腎臓より下流の尿路に閉塞が生じている腎後性急性腎障害では、泌尿器科が専門領域となるため、密に連携し、情報共有を図りながら治療を進めていきます。
急性腎障害の予後
急性腎障害は、進行すると生命を脅かす状態に陥る可能性があります。ただし、適切な治療を迅速に行ったとしても、腎機能が完全に回復するのは患者様の3割程度です。残りのうち約6割は腎機能が十分に回復せず、慢性腎臓病(CKD)へと移行します。さらに、約1割の患者様は腎機能が完全に失われ、透析治療や腎移植が必要となります。
腎機能の回復予後は、個々の患者様の状態によって大きく異なるため、一概には言えません。特に高齢者の場合、急性腎障害を発症すると、完全な回復はより困難になる傾向があります。いずれにせよ、早期に適切な治療を受けられるかどうかが、その後の経過を大きく左右します。少しでも異変を感じた場合や、健康診断などで異常を指摘された場合は、速やかに腎臓専門医の診察を受けましょう。



